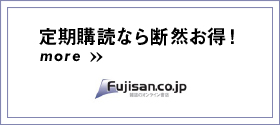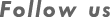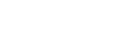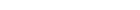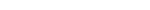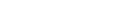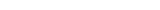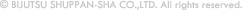秋山 まりえ
日本在住/ステラマリー代表
総合商社勤務を経て、2006年に資格取得。ソムリエールとして経験を積む。2015年、ステラマリー起業。同年より「ステラマリー☆ワイン会」主宰。メーカーズイベント、ペアリングディナー開催等、ワインが繋ぐ一期一会をプロデュース。『ワイナート』誌106号〜116号にて「a Story」対談連載。

a Story☆☆
『Winart』で足かけ4年にわたり連載された「a Story」が装いも新たに復活。いま気になるワインパーソンに逢いに行く。第2回のゲストは、夫・嘉晃と二人三脚でサトウ・ワインズを運営する佐藤恭子。ピノ・ノワールの銘醸地セントラル・オタゴにワイナリーを構え、ニュージーランド、修行先のフランス、そしてナチュラルワインへのリスペクトを貫き、独自のワイン造りを続ける。メーカーズディナーのため来日した彼女に訊く。

■menu1
antipasto「出逢い」

秋山 ご主人の嘉晃さんとはお勤めの銀行で知り合われたとの事ですが、その頃、おふたりともワインはお好きでしたか。
佐藤 同じ部署でした。まだ1990年代、日本はイタメシブーム。私はイタリアワインを楽しく飲むだけでしたが、主人はもうマニアックにハマっていましたね。結婚後、主人はイギリスに赴任。私は銀行を辞めていたので、一緒にロンドンへ。そこで世界中のワインに触れ、週末はフランスなどに出かけたり、産地で収穫を手伝わせていただく機会を得て、どんどんワインが身近になりました。日本に帰る頃には主人は「ワインを造りたい」という気持ちが自然に強くなっていました。そして、私は帰国後インポーターの仕事に就いたんです。そのときに、自然派と呼ばれる生産者のナチュラルワインに出逢ったことが大きかったですね。
秋山 まだ「自然派」という言葉が出始めた頃ではないですか。
佐藤 2004年くらいですからね。試飲した残りのワインを持ち帰って、主人とふたりで飲んだりしていました。繊細なナチュラルワインが沢山ありました。まだ未知のワインでしたが、あのときに生まれた大きな感動がいまのワイン造りにつながっています。
■menu2
primo「飲み頃」

秋山 サトウ・ワインズさんのワインは、骨格がしっかりしているけれど、優雅。口当たりがとてもなめらかで、酸とのバランスがすばらしいと思うのですが、醸造にあたっては、どこに重きを置いてますか。
佐藤 そうですね。ワイン造りはあくまで人の技ではありますが、風土を反映したブドウそのものの個性・味わいがワインに映し出されるようにしたい。これが私たちの想いですね。そういう意味で、収穫のタイミングの見極め、これがいちばん重要ですね。また、いつ瓶詰めするかも大事です。しっかり熟成期間をとること。それがサトウ・ワインズのスタイルなんですが、ワインをしっかり安定した状態にしてあげることで、瓶詰め後に安定した状態で飲め、熟成も可能になる。
秋山 ブドウありき、ですね。いかに自然のまま、私たち飲み手までもっていくか。
佐藤 なおかつ、自然な造りのワインには飲みづらいものもありますから。フィロソフィーを押し付けて、あまりいい状態ではないもの飲み手に届けることになってしまうのは避けたい。やはりワインはキレイでないといけない。
秋山 私たち飲み手が望んでいるのはまさにそういうことなのだと思います。
■menu3
secondo「終わりがない」

秋山 ワイン造りに携わるようになって、どのような変化がありましたか。
佐藤 考えたこともないですけど……終わりがないですよね。つねに……。
秋山 育ててるわけですからね。生きものですから手がかかりますよね。
佐藤 終わりがない。私は畑仕事が好きなんです。日本ではずっと都会で生活していたので大好きだし、時々日本に戻ってくると都会って楽しいなって思うんですけど、畑仕事がそれ以上に楽しくて、飽きない。つねに新しいことを発見したりして、興味が尽きない。いつまでも終わりがないからでしょうね。
秋山 きっと天職なのだと思います。
佐藤 あと、いろいろな方々と年齢を問わず、ワインを軸に出逢えること。
秋山 私もまったく同じです。ワインで人と人とはつながりますね。
佐藤 北半球のワイナリーのご子息が勉強に来たりするんですよ。すごく若い子たちともワインでつながることができる。それはとてもありがたいことですね。もと居た立ち位置からは考えられないことです。自社畑でワイナリー、それもニュージーランドでなんて!
■menu4
dolce「ふたりだから」

佐藤 ふたりでこなしているものですから、規模も小さいですし、できることも限られています。いろいろなことを一気にはできません。自分たちが現実的にできることを考えながら、日々を送っています。主人と私はかなり違うタイプで、ワインについても意見が合わないことも。でも、不思議なもので、最初は、それは違うなと相手に対して思っているのに、気がつくと段々と近づいているんです。
秋山 そんなおふたりだからこそ、このワインなのだと思います。ご主人だけでも、恭子さんだけでも、別なものになっていたのではないでしょうか。
佐藤 そうかもしれないですね。小さなことひとつひとつの決断がワインの味わいに付与しているのだと思います。ブドウを育てているときは、ほんとうに幸せです。芽が出て、花が咲いて、ブドウが実って……その行程を追いかけるのが幸せなんです。冬も好き。剪定も大事な仕事ですから、楽しみにしています。

佐藤恭子(右)
Kyoko Sato
銀行勤務時代に知り合った佐藤嘉晃と結婚、ワイン造りを志す。インポーター時代に出逢ったナチュラルワインに衝撃を受け、後に、フィリップ・パカレ、ジュリアン・ギュイヨ、クリスチャン・ビネールでワイン造りを学ぶ(夫とはあえて別のワイナリーに赴く)。2009年、サトウ・ワインズ設立。16年、自社畑植樹。19年、ワイナリー完成。自社畑からの「ラフェルム・ド・サトウ」もスタート。
■Marie’s マリアージュ

ご主人の佐藤嘉晃さんには以前、メーカーズディナーの際にご挨拶していますが、佐藤恭子さんとは初対面でした。物静かで落ち着いた恭子さんのお話を聴くほどに、おふたりで切磋琢磨されてきたことを感じます。意見を出し合って、たったひとつのワインを造り上げていらっしゃる。
ワイン名にも表れていますが、フランスワインへのリスペクトとともに、独自のスタイルへのこだわりを感じます。造りたいものが明確にある。しっかりした芯がある。味わいは繊細ですが、決して骨格の細いワインではない。そこに、いわゆる自然派の枠にはおさまらない「冒険」が感じられます。恭子さんの凛とした佇まいは、エチケットの「Sato」の書の力強さとワインそのものにフィットしていることに、あらためて気づかされました。
現在、コースで供する焼鳥店のほとんどは、レバーなどを除けば塩が中心です。やはり焼鳥には白ワイン。ワインのミネラル感と焼鳥の塩味(えんみ)の調和を、サトウ・ワインズのリースリング(Sato Riesling L’atypique 2021)で再確認しました。ニュージーランドのワインは果実が完熟し、ボリュームが強めですが酸がしっかり支えており、最後までマリアージュが持続します。
サトウ・ワインズのリースリングはやはりフランススタイルでエレガント。ペトロール香もごく微細に感じられますが、逆にそれが炭焼きの香りに合います。白い花やミツのニュアンスは、鳥料理全般と相性が良いと思います。ドライな中にもフルーティさが際立つリースリング。コースの最初から最後まで、ワインと焼鳥が5:5(フィフティフィフティ)でした。
6:4ぐらいの割合で、ワインと料理、どちらかがどちらかを包み込む組み合わせが多い中、これはフィフティフィフティという奇蹟的なマリアージュ体験でした。
サトウ・ワインズ
https://www.satowines.com
写真:秋山まりえ、相田冬二(menu1、2、プロフィール)
構成:相田冬二

![[ワイナート]The Magazine for Wine Lovers](https://winart.jp/winart_kanri/file/img/common/img_header_winart.png)