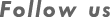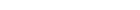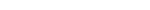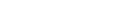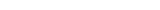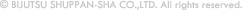山田マミ
日本在住/ワインフィッター®/La coccinelle 代表
フランス留学をきっかけに、ワインとの出会い。フレンチレストラン店長、ワインインポーター、webワインショップのライターを経て独立、2013年よりワイン販売業を開始。これまでになかったワインの職業名【ワインフィッター®】を商標登録。企業向けワインイベントのプロデュースや、店舗をも持たず在庫を持たず、お一人おひとりのニーズに合わせた全く新しいシステムのワイン小売販売を行っている。自身の経験を生かし、ワインフィッター®という新しい働き方の普及にも力を注ぐ。 https://www.lacoccinelle-vin.com/

【連載 第29回】 CAVE D’OCCI 掛川 史人 ゼロから挑むシードル造り〜2022年産シードル完成!

2019年からスタートした新潟カーブドッチワイナリーの醸造長 掛川史人によるシードル造りへの挑戦。22年の造りは4年目となり、「ゼロから」と付けたタイトルは相変わらず「初心者です」と言い訳をしているようで、もはや掛川にとっては違和感があるかもしれない。
4年を経たからこその思いを、彼は22年産シードルを試飲しながらこう語った。
「今年の出来はまったく悪くないし、むしろ3年前なら鼻高々で満足していたと思う。でもまだ越えられない壁があるなぁ、という感じ」。
経験を積み品質が上がれば醸造家が目指すレベルも同時に上がり、決して交わることはないのかもしれない。4年目となっても彼の口から「満足」の言葉を聞くことはむずかしいだろうか。掛川の22年産シードル造りを取材した。
最初に伝えるべきは、22年産は1種類のみの製造だったということ。前年の21年産は、ワインユーザーをターゲットにした750mℓボトル入りのcidre(シードル)と、ビールユーザーを意識した330mℓボトル入りのcider(サイダー)の2種類を製造した。後者のサイダーは摘果果を使用して酸味を効かせ、ホップが香る味わいだったが、毎年原料を提供してくれる長野の小林農園では22年は収穫量の減少により摘果の回数が減ったため、充分な摘果果原料が確保できなかった。結果、22年は750mℓボトル入りのcidre(シードル)のみの製造となり、それは前年に引き続きカーブドッチの人気シリーズ「FUNPYファンピー」のひとつとしてリリースされた。

摘果果は手に入らなかったものの、小林農園から届いた通常の生食用フジは約5トン。それに加えて、岩手県陸前高田市にあるワイナリー、ドメーヌ・ミカヅキの及川恭平が管理するリンゴ畑から、摘果をせずにならしたままのいわゆる「無摘果」のフジが約1トン届いた。
摘果果とともに掛川が注目する小玉の無摘果果。どちらも毎年安定的にシードル原料として確保するには農薬散布のタイミングや隔年結果などの課題をクリアせねばならないが、果汁分の多い生食用リンゴだけでは得がたい酸味と凝縮感を補完するために必要な原料と掛川は考える。22年は摘果果の入手は断念したため、及川から届く無摘果果に期待を寄せていた。
合計6トンの原料はまず3ロットに分けて仕込まれた。最初に半量ほど届いた小林農園の生食用フジを第1ロットとして搾汁、デブルバージュ(固形物の沈殿)後、シードル用の酵母を添加する前段階で乳酸菌を投入し酢酸を生成した。果汁だけでは得られない酸味の補完が目的である。
その後届いた生食用の半量は、第2ロットとして搾汁、デブルバージュ、酵母添加を経て発酵が始まる段階で、及川から届いた無摘果リンゴが皮付きのまま丸ごと投入された。表層はまるでリンゴ風呂のようにゴロゴロと小玉リンゴで埋めつくされ、それが何層にもなるほどの量だという。浸漬期間は約1週間。掛川にとってシードルでは初めての試みとなる「マセラシオン製法」だった。そして1週間後に取り除かれた無摘果果を搾汁、発酵、これが第3ロットとなった。

23年1月に仕込まれたこれらの3ロットはその後アッサンブラージュされ、6月に瓶内二次発酵を経て瓶内熟成期間に入った。取材に新潟を訪れたのは8月後半。冒頭の掛川のコメントはそのときのものだった。つまりは瓶詰めから2カ月足らず。掛川が望むミドルからアフターへ膨らむ酸や余韻はまだ弱く、それを「越えられない壁」と表現しているようだった。
瓶詰めをしてしまったここから何かを液体に施すには限られている。強いていえばデゴルジュマンで澱を引き、よりクリアなリンゴ感を引き出すくらいか? しかしながら8月からはワイナリーにとってワイン造りが最盛期。約4000本のシードルのデゴルジュマンに人員を割く余裕は正直ない。
「1年目のシードルを2年後に開けたとき、荒削りだった味わいがバランスよく落ち着いていてその変化に驚いたんです。シードルは短期間の瓶熟成でもだいぶ変わるようなのでリリースまでのあと数カ月、このまま静置して瓶熟成の可能性を見守ります!」、掛川はそう語っていた。

真夏の取材から3カ月後の11月、「FUNPYシードル 2022」はリリースされた。掛川にその3カ月間の経過を尋ねると、
「思った以上によくなりました!(笑)。この数カ月、試飲するたびに香りが開いて味わいもよくなり、まとまりも出て、瓶詰め直後とはだいぶ違う印象です。すでに販売したお客様からも評判は上々です」。
酢酸系の酸味も存在感を増し、マセラシオンした無摘果リンゴの皮のニュアンスもしっかりと心地よい渋みの余韻となっていた。また15パーセント程度の割合ではあるが、第3ロットの無摘果リンゴの液体が全体にぎゅっと凝縮感をもたらし「いい仕事している!」と掛川は表現した。
結果的には瓶内熟成と無摘果果の「いい仕事」によって、22年の出来におおむね満足感を口にした掛川だが、瓶内熟成は不確定要素が多く、無摘果果は今回入手できなかった摘果果と同様に原料調達が不安定である。それらに頼りすぎず、醸造家主導の良質で安定的な造り方を掛川はすでにいくつか模索していた。
「次に試してみるとしたら、ひとつは酸味の補完にサワー系の酵母を使ってみるとか。ふたつ目は液体を加温してみてベイクドなニュアンスが出るかどうかとか。ワイナリーに導入した蒸留器は加温が可能なため、そんなことも試せるかもしれません。あとは、とある北海道のシーダリーから聞いた製法ですが、搾汁後のデブルバージュののち、さらに濾過をしてよりクリアな果汁にしてから発酵させる。そうすることでよりでき上がりのリンゴ感が増すようなので、それも作業に無理がなければやってみたいですね」。
そしてさらに掛川が挑戦してみたいと挙げたのは「天然酵母」によるシードル造りだ。しかしそれは、いわゆる自然派を意識したアプローチとは異なる。
「原料である果実の内包している要素が多い場合には、培養酵母でもよいけれど、リンゴの液体のようにそれほど要素が多くなく優しい場合には、培養酵母を使うと要素が抜けすぎてしまうので、天然酵母の方がよいかもしれません。品種によっては、それはブドウにも言えると思います」。
「ブドウにも」ということで、23年のワインの仕込み期間中には天然酵母と培養酵母の違いによるさまざまな造り分けを試みたという。同じ品種でも酵母の違いによってどの要素がプラスとなりマイナスとなるのか。どちらの酵母を使うことが、目指すワインのコンセプトに合っているのか。長所と短所を把握することで、それらを補いながらより完成度の高い味わいが目指せるだろうか。そんな仮説と検証を繰り返しながら、23年の仕込み期を過ごしたという。

醸造所には培養酵母も生息しているため、
醸造所以外の場所でブドウ品種ごとに酒母(スターター)を仕込み、
より純度の高い天然酵母をわかせる試み。
「僕はフィロソフィーとして“天然酵母がいいですよね”ということではなく、そもそもの目指すワインのプロポーションと、品種に対する理解、ヴィンテージの特徴を見て天然と培養のどちらが適正なのかを選択したい。たとえば23年の“どうぶつシリーズ”は全キュヴェを天然酵母で仕込みましたが、“FUNPYシリーズ”は求めるコンセプトが楽しくて陽気な液体なので、天然だけだとエネルギーが少し弱い気がする。4年間シードル造りと向き合って、酵母の選択は哲学ではなくツールだと考えることができるようになりました。ワインもシードルも、目指す味わいへ向かう選択肢が広がったような気がしています」。
新たな「選択肢」を得た醸造家 掛川史人が生み出すワインとシードル、どちらもこれからのさらなる進化に期待が膨らむ。

絶賛発売中!
「FUNPY シードル(Cidre) 2022」
希望小売価格:2970円(税込)
購入はこちらから→https://www.docci.com/online-shop/

![[ワイナート]The Magazine for Wine Lovers](https://winart.jp/winart_kanri/file/img/common/img_header_winart.png)