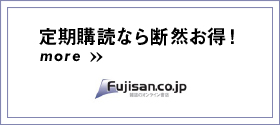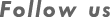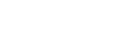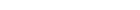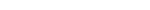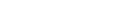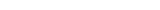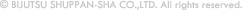キリノカの新設ワイナリーにて唎き、語らう主流のピノ・ノワールと新参のブドウたち
長野県塩尻近郊の冷涼地、小野をピノ・ノワールの栽培最適地と見定め、2023年からワイン造りをスタートさせたキリノカ ヴィンヤーズ&ワイナリー。24年には遅霜という痛烈な自然の洗礼を受けたが、栽培醸造家の沼田実はアイデアを駆使しワイナリー運営継続の道を切り開く。そんなキリノカの現状を知るべく、ワインスクール講師やコンクール審査員として活躍する楠田卓也がワイナリーへ。1年の熟成を経たキリノカの初ヴィンテージ2023を確認しつつ、「諸事情によって」一気に増えた2024ヴィンテージの複数アイテムを試飲、さらには沼田との対談でキリノカワインの明日を予想する。

■ピノ・ノワール専門から新境地へ
2024年初夏に自前のワイナリーを完成させたキリノカは、理想的な糖度に到達した昨年の大豊作を踏まえ、今年は1200リットルのピノ・ノワールを仕込めると踏んでいた。当主の沼田実はピノ・ノワールに強いニュージーランドの大学で醸造と栽培の学位を取得し、オレゴンのチェハレムなどピノ・ノワールの名門ワイナリーで経験を積んだ人物。日本でのワイン造りも当然ピノ・ノワールに特化するつもりで、自社畑に植えたのはピノ・ノワールと少量のシャルドネのみだ。しかし、5月の遅霜で新芽がダメージを受けほぼ全滅、収量は大幅減。
いかんせん、後ろ盾となる大企業スポンサーなどもたない独立独歩のワイナリーである。ピノ・ノワール不作の今年、連携を取り合う長野の栽培家仲間に融通してもらったメルロ、カベルネ・ソーヴィニヨン、ピノ・グリ、さらにはシラーの醸造にも新規挑戦する決断を下した。
今年1月にキリノカのワインをテイスティングした上で沼田と語り合った楠田卓也は、その後も標高850メートルの畑へ足を運び、作業を手伝いつつブドウ樹の生育を間近で観察してきた。「まだ小野のテロワールを語るほどのデータは集まっていないけれど」と楠田は前置きしつつも、新設ワイナリーであらためてテイスティングすることで、キリノカのヴィジョンはだいぶ掴めてきたようだ。
さっそく、各ワインのテイスティングコメントを含め、両名のトークに耳を傾けてみよう。
■キリノカの核となるピノ・ノワール、2023と2024のいま

楠田 ワイナリー内は、脚が長く背の高いタンクがあったり、小~中サイズのタンクが充実していたり、とユニークな構成ですね。
沼田 作業動線を考慮した上で、小ロットで細かく仕込めるようオリジナルで設備を整えました。昨年までは委託醸造で、今年がこの自社ワイナリーでの初醸造です。さて、11月の4週目に樽詰めしたばかりのピノ・ノワールから試飲をスタートしましょう。いまはまだまだ香りが閉じ気味でしょうが。

楠田 フレンチオークの小樽ひとつ分、これがキリノカ2024ですか。
沼田 楠田さんも知っての通り、今年2024のピノ・ノワールはちょうど新芽が出始めた5月の遅霜で大打撃を受けました。結果、わずか120リットルを最高レンジ「ドメーヌ・キリノカ」名で、残りのワインはよりカジュアルな「小野ルージュ」名でリリースすることとしています。

楠田 2023にはなかった酸のキレがブルゴーニュを感じさせます。北海道産とはまた違う、長野・小野のピノ・ノワールらしさがあります。
沼田 2024は、理想的な糖度まで上がった2023ほどの偉大な年ではありません。しかし、2024のように昼と夜の温度差が大きい10月中旬まで収穫を待つと、ブドウが完璧に熟すことは確認できました。世界最高のピノ・ノワールができる可能性が、またひとつ高まったのです。

楠田 2023のほうは、300リットルのオーク樽を使った「メゾン・ド・キリノカ キュヴェ零」、228リットルのオーク樽を使った「メゾン・ド・キリノカ キュヴェ壱」の2種類ですね。樽が違うだけとは思えないほどキャラクターが異なりますが、それぞれ瓶内熟成でよく育っています。以前の試飲から比べるとまったくの別物。
沼田 「零」と「壱」、好みは分かれるでしょう。収穫から1年経った現時点で香りが開き始めているのは「壱」のほう。
楠田 リキュールにも通じる果実の濃縮感、オークのニュアンスも強めな「壱」は、もうちょっと置くとさらになめらかになるはずです。どちらにせよ、果実味豊かでエレガント。まず日本の長野でこれほどのピノ・ノワールができることに驚きです。

沼田 さきほど2024のピノ・ノワールがブルゴーニュ的な酸だとおっしゃいましたけど、価格高騰でブルゴーニュワインが入手しづらくなった方々へ、ブルゴーニュの代替としてこのワインは提案できそうでしょうか?
楠田 充分に代替のひとつとなり得ると思います。将来的にブルゴーニュのグラン・クリュと並べても遜色ない可能性があるのでは。
■圧倒的な厚みある、いままで日本になかったシャルドネ

楠田 ピノ・ノワールは以前にも試飲したことがあり、熟成が進んでもある程度予想はついたのですが、今回の訪問でいちばん衝撃を受けたのは24年のシャルドネ。樽で熟成中のシャルドネは、どっしり存在感のある厚みというより、風味が真ん中に集中し立体感をもたせるような風味の形が特長的でした。酸があるので、重さを感じないのです。補酸したのでしょうか?
沼田 いえ、していません。加えて、スムースに流れるだけではなく何かインパクトがあるような味わいもありませんでしたか? 私は土壌に由来するものかと予測しているのですが。

楠田 粘土質が少なめ、とか?
沼田 基本はローム層ですが、自社畑のなかでもシャルドネを植えている北小野区画はカルシウムが多く、そこはスッと抜けるような味わいにつながると思います。ただ、礫と鉄分の多い小野区画の畑のシャルドネをブレンドしていまして、そちらがピノ・ノワールにも共通するような苦みにつながっているのではないかと。たとえば、モンラッシェが鉄分の多い赤色の表土の畑で白ブドウを栽培していますよね。そのおかげで、重心が低い味わいというか……。
楠田 いやいや、フルーツの風味が立ち昇る部分をとらえると、かえって重心は高い印象です。ブルゴーニュよりもカリフォルニアを代表するシャルドネのひとつ「キスラー」のマクレアを彷彿とさせるというと褒めすぎかも知れませんが、ニューワールド的なクラシック・スタイルとも言えるでしょう。
■どの品種にもピノ・ノワール専門家らしさがあふれる
沼田 さて次は瓶詰前の「杜音 オゴッソ ピノ・グリージョ&シャルドネ」「杜音 オゴッソ メルロー ロゼ」をどうぞ。オゴッソは信州の言葉で「ごちそう」を意味していまして、よりカジュアルなラインをオゴッソ・シリーズとしてリリースしていく予定です。
楠田 最高級ワインではなく、かえって安いレンジでどう造っていくかが大事。ワイナリーの真価が問われるところです。
沼田 3,000円台となると一般的には安価とされませんが、それでも長野県のカジュアルな飲食店で長野産ワインを味わってほしくて新設したシリーズです。白は当初、ピノ・グリージョを単一品種のままワインにしようとしていましたけど、飲みやすさを重視してシャルドネをブレンドしました。カジュアルワインは、どんな食事とあわせても、さらには食事と合わせず単体で飲む場合でも、楽しく飲めないといけませんから。
楠田 ピノ・グリージョには果皮からくるフェノレの香りがあり、シャルドネとのブレンドはいいアイデアだと思います。肉でなく魚、それもサバやイワシの塩焼きが食べたくなるワイン。

沼田 あれ、たしか発注したボトルの裏ラベルには「鶏肉料理に合う」と書いたような記憶が(笑)。でもおっしゃる通り、青魚や、蕎麦粉のパスタのようにちょっと苦みのある食材は合いそうです。そしてロゼのほうはメルロ100パーセントですが、セニエとダイレクト・プレスをブレンドしています。
楠田 キレイな色調で、果物のニュアンスが浮き立つ味わい。酸はやや控えめで、飲みやすいですね。
沼田 醸造時の温度コントロールで、果実の個性をバランスよく表現した結果です。続けて、桔梗ヶ原シラー、安曇野のカベルネ・ソーヴィニヨン、そしてメルロをテイスティングしてみてください。

楠田 シラーはまだ少し閉じ気味ながら、果実味が前面に出て、クールクライメットシラーに期待する黒粒コショウも出てますね。カベルネ・ソーヴィニヨンも、メトキシピラジンの香りはありません。タンニンのテクスチャーがキレイで、アルコールと果実感のバランスも見事、たいしたものです。これは、どういったスタイルを目指しましたか?
沼田 予定外で急に入手できた品種ですから、最初に何かイメージをする間もないまま手探り状態で仕込みに入りました。キリノカは、果実味を出すためのコールド・マセラシオンをハウスルールとしています。白にしても赤にしても、またナイト・ハーヴェストだとしても、いったんは冷やすのがお約束です。カベルネ・ソーヴィニヨンなんて今回生まれて初めて仕込んだ品種なのですが、どうやら長時間冷やすとメトキシピラジンやタンニンが強く出るようで、どこまで冷やすべきかとても迷いました。
楠田 メルロのほうも、ブドウの供給元が造るメルロのようにしっかりタンニンがあるタイプではなく、水には溶出させて、アルコールでの抽出は避けたようですね。
沼田 はい、種からのタンニンが出てくる発酵後の醸しは短めに。どうしても、抽出しすぎるのが怖くて。
■キリノカのワインが魅せる三大ポイントとは?
楠田 私の感想をひとことにまとめると、「さすが、どの品種でもピノ・ノワールの造り手らしさが出ているワインだな」。私の弟、楠田浩之もニュージーランドでピノ・ノワールに力を入れつつ、シラーや一度だけメルロを醸造していますが、その「クスダワインズ」とキリノカのワイン造りは、控えめな抽出とキレイさという点で同じ方向性だと感じました。

沼田 光栄です!
楠田 どちらも、けして薄いわけではないのです。今年1月のキリノカ訪問時、日本のピノ・ノワールでよく評される「薄うま」との表現に触れつつ、キリノカのワインはけして「薄うま」タイプではないとの点で意見が一致しましたよね。
沼田 1品につき1杯というペアリング企画なら、濃厚なワインでもおいしく飲めます。でも、飲み続けられるワインとなると、濃すぎてはいけません。そこで、日本の食生活には「薄うま」が適していると思われがちですが……。
楠田 誤解されているのが、「薄うま」の「薄」ですよ。天ぷらやとんかつなどを例外として、和食は基本的に洋食より油脂がなく、水分が多め。油脂が多い料理を食べると口のなかが油脂でコーティングされ、濃厚なワインが必要になります。いっぽう油脂が少ないと、風味が強くないエレガントなワインのほうが好まれます。でも、日本だからといって薄い味のワインは、ワインとして正しくないのです。まず果実味があって、軽めでも風味豊かなワインでなくてはいけません。

沼田 うちでは、キレイな果実味にいちばんポイントを置いて栽培醸造しているつもりです。
楠田 今日の試飲で、キリノカのワインすべてに「フルーツ感」「クリーン」そして「密度」との三大ポイントを見出すことができました。沼田さんの狙い、きちんとかたちになってワインに表れていますよ。

キリノカ ヴィンヤーズ&ワイナリー
長野県上伊那郡辰野町小野1305-1
TEL:0266-75-0574
https://kirinoka.com
Photo : Junichi Miyazaki
Text : Jo Yamamoto

![[ワイナート]The Magazine for Wine Lovers](https://winart.jp/winart_kanri/file/img/common/img_header_winart.png)