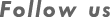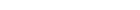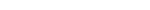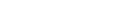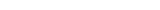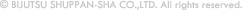【短期連載 第2回】パリに恋して、パリに試される。日本人女性初の仏ミシュラン一つ星に輝いたシェフの軌跡と奇跡。
2019年1月21日に発表された「ミシュランガイド フランス 2019年版」で、日本人女性シェフとしては初の一つ星に輝いたひとがいる。この快挙を成し遂げたのは、パリ12区にある「Virtus」(ヴィルチュス)の神崎千帆シェフだ。 世界グルメ激戦区のパリで、他国の女性シェフがこの栄誉に辿り着くのは並大抵のことではない。彼女の道のりと想いに、コンサルティングやイベント開催などを手がけ、枠にとらわれずにワインの可能性を探るステラマリーの秋山まりえさんが迫った。秋山さんは神崎シェフの修行先「Mirazur」(ミラズール)時代から親交がある間柄。女性同士の語らいだからこそ見えてくるものが、ここにはある。 対談が行なわれたのは2018年11月8日。つまりミシュラン一つ星を獲得する2カ月以上前のこと。デジュネを終え、ひと息ついたところで始まった貴重な対談を、10章形式、全5回の連載でお届けする。

第3章
すべては「たまたま」
そのときどれだけ
本気で取り組めるか
神崎千帆(以下C) 私、渡仏歴が2回あるんです。
秋山まりえ(以下M) そうでしたね。
C 最初、20歳の頃、2年くらい。そのときは女性ということと、フランス語が話せない、そしてテクニックが足りないということで、日本で技術を磨いてからもう一回フランスに戻ろうと思ったんです。初めてフランスに来たのは2000年。いまみたいに20代前半で渡仏する人はあまりいませんでした。みなさん30代中盤で。
M (日本で)経験を積んでから、という方が多かったでしょうね。それを20歳で、というのもカッコいい!
C たまたまです。私、その当時お付き合いしてた方がフランスに行っていて。その追っかけで行ったんです。あのときはほんと、バカになってました(笑)。
M 若いんですもの。
C 若気の至りです。とにかく、行っちゃったんですよ。その当時は周りの人にもすごく反対されて。彼に迷惑かけるようだったら、すぐに日本に帰れ、と。うちの母にも言われました。そういうこともあって(気持ちの上では)絶対帰れない! という感じだったんですけど、2年くらい研修させていただいて、本当に痛感したんです。このままじゃ自分は絶対に通用しないなと。日本に一旦帰って、日本人としての技術を身につけてから、もう一度フランスに行こうと思った。当時、大倉山・クール・オン・フルールの奥田勝シェフ、渋谷・ミラヴィルの都志見セイジシェフ、銀座・朱のオーナーソムリエの宮川陽子さんに大変お世話になりました。
5、6年経ち、フランスの地方の、ミラズールではない二つ星のレストランに。フランスに戻ったのは2007年ですね。そこではスタッフが全員、二つ星、三つ星クラスの経験者ばかりなんですよ。みなさん、(料理界の)エリート中のエリートで。自分が入ったときは「誰?」という感じ(笑)。しかも、女性。じつは最初、女性という時点で一回、断られたんです。でも、すごく粘った。ずっと行きたかったお店だったので。で、ようやく入らせてもらって。でも、(研修中は)どれだけアピールしても、ポストを上げてもらえなかったんです。
M あぁ……
C そのときに思ったんですよね。自分の(担当の)仕込みは終わっているのに、なんで休憩時間に仔羊をおろしたり、そういうことをさせてもらえないんだろう? と。いまから思えば、当時のスー・シェフは研修生の私に朝から晩までずーっと残って16、17時間労働させるわけにはいかなかったんです。いま、責任者という立場になるとわかるんですけど。その当時は本当に悔しくて。なんで、させてもらえないんですか? という気持ちが強かった。
そこでの研修を終えて、さあ、どうしようかな、といくつか手紙を出した数軒のうちの1軒がたまたまミラズールだったんです。その頃はミラズールも全然有名ではなくて。たまたま行って。たまたまマウロに気に入ってもらって。いまに至る、みたいな。2007年、これも「たまたま」なんですけど、当時のミラズールはスタッフが揃っていなかった。もし、あのとき、スタッフが優秀な男性たちばっかりだったら……いまの自分がこうしていられるかどうかもわからない。
そもそも女性はポストに入れてもらえないんですよ。女性というだけでまずは大抵、パティシエにまわされる。その後は前菜(アントレ)の担当になる、というパターンなんですけど。でも、たまたま、当時スタッフが足りてなかった。それで、すぐにポンポンポンと(ポストを)上げさせてもらって。
M そのときは部門シェフですか。
C コミとしてパティシエを2日間やって……
M 2日間!(笑)
C これもたまたまです。ミラズールってけっこう野草を使うんですよね。
M そう、裏庭の。
C 野草を知らないと仕事にならない、通用しないなと。入った初日の休憩時間に庭におりていって、写真撮ったりしていたんです。それをたまたまスー・シェフが見ていて。「何やってんの?」と。「野草を勉強しないと、このレストランはたぶん無理だと思うので」みたいな話をしたら、その話をマウロに伝えてくれたみたいで。
M すごい。
C そこから「野草」のポストに。そのポストはみんな、嫌いなんですよ。
M 大変?
C ええ。朝からずーっと野草を探して、洗って、キレイにして、手入れして。かなり大事なことなんですけど。
M あのレストランが大事にしていることを、千帆さんはすぐに感じとった。それが素晴らしいし、センスだと思います。これは日本人というより、千帆さん個人の繊細さだから。
C まあ、みんなが嫌がるポストだったからですよ。当時は(マウロ)シェフも怖かったので、みんな、直接は(疑問点を)訊けないんですよね。でも私は、これ、絶対訊かないと、わからなくなる。シェフを避けて別なひとに訊いたら、余計面倒なことになる。そう思って、直接シェフに訊いていったんです。これは何ですか? これは何ですか? と。マウロも、「なんだ、こいつ」と思ったんじゃないですかね。じつはこれ、日本で失敗していたからなんです。日本にいたときは、シェフが怖くて(わからないことも)何も訊けないような感じでした。同じ失敗を何度も繰り返しました。シェフにしてみたら「なんで訊かないの?」ということだと思うんです。日本でやったすべての失敗を、もうフランスでは繰り返せない。そう思っていました。
M 経験、なんですね。
C 日本でのあの経験がなかったら、また同じことになっていたかもしれません。

le monologue de Marie trois
couleur
色彩
これぞ千帆さん。私がもっともそう感じたのが、帆立やカリフラワーなどを使った前菜。バルサミコの酸がほどよく効いて、ドイツの辛口リースリングがよく合いました。まるでお花畑のような愛らしさ。その色合いにはマウロさんの世界観も感じますが、ミラズールはもう少し男性的です。
そして、そのこと以上に、たとえばハーブを使った細かい手作業を大切にする。ミラズールに足を踏み入れた修業初日から、マウロさんがいかにハーブを大切に扱っているかを察した千帆さんだからこそ、そうしたマウロさんのスタイルを、彼女ならではの方法で継承していると思いました。
食材それぞれが、大きさを合わせるようにカットされています。しかもキューブ状ではなく、面取りしているかのようなボール状。薄くカットされた素材とともに、お料理に立体感を出しています。しかも、食べやすい。丸いフォルムのお皿がまた、ちょうどいいサイズ。全体のバランスが素敵ですね。
以前の、イチゴとアスパラの前菜も記憶に残るものでしたが、ここでも千帆さんならではの色彩センスが活きています。ほかのどこにもない千帆さんのオリジナルのひと皿ですね。
温度感のむずかしいお料理だと思いますが、そのキープも素晴らしかったですね。ほのかに温かい。いただいたのは11月でしたから、これもありがたかった。見た目はサラダのようでもありますが、冷たいお料理ではありません。ソースもほんとうにいい色ですね。グリーンのようでもありゴールドのようでもあり。「デセール?」と思うひとがいてもおかしくない美しさです。
最初に見たときの予想が、いい意味で裏切られる。これも食べ手にとっては幸せなことです。
第4章
たとえ遠回りしても
最後まで諦めない
道はひとつだけ
C で結局、「野草」のポストにも2週間しかいなかったんですけど。
M すごい(笑)
C その後は、冷前菜、温前菜のポストもいただいて。シェフは私のやる気を感じてくれたようでした。ちょうどビザが切れる頃だったので「もし、次にビザが取れたら、お肉のポストに上げてあげる」と。当時、28だったんですけど、どのレストランでもお肉のポストはやったことがなかったんです。
M 興味ありました?
C 興味はありましたけど、半分以上はコンプレックスですよね。28でお肉のポストをやったことがないというのは(料理人として)かなり遅いほうだと思うんですよ。始めたのが26歳とかなら仕方ないですけど、私、料理を始めたのが18だったので。なので気持ち的にはかなり切羽詰まってました。その切羽詰まっていたのが逆によかったんだと思います。
M きっとそうですね。
C 絶対に失敗できないっていうのがあったんで。
M ギリギリのところ。
C そう。私の周りも、オレオレ系のイタリア人の子たちでしたからね。これ、失敗したら、絶対ポスト取られるなと。なので、かなり集中して朝から晩までお肉のことを考えていました。お肉の部門シェフの終わりかけに、マウロがスー・シェフの話を持ちかけてくれたんですが、自分的には技術が足りないと思ったので、もう1年、お肉をやりたいとお願いして。1年後、また「スー・シェフやらない?」と言ってくれたんですが、魚をやったことがなかったので、「魚をやらせてほしい」と。魚の部門シェフを1年やりました。
料理の世界って、仕事ができないと、周りにすごく言われるんですよ。下の子たちにも。それを(厨房で)たくさん見てきたので。しかも(自分は)女性だった。どの部門も100%できないとバカにされるし、(スタッフが)いうこときいてくれないなと。なので、スー・シェフになる前に全部のポスト、回りたかったんです。
M なるほど。
C 魚のポストを1年やってから、ある程度、準備ができたかなと。で、まりえさんと出逢う2011年にスー・シェフになったんです。
お料理の世界は本当に瞬間、瞬間で進んでいきます。失敗しました、もう1回、というわけにはいかない。お客様も(料理を)待っているので。自分が(仕事を)見せていかないと、下の子も「このひと、大丈夫?」と思っちゃいますよね。結局、かなり遠回りをしましたが、それが自分には合ってたかなと思います。才能がある方は、24、25でシェフになります。でも、自分にはそういう才能はなかったので、遠回りは遠回りですけど、自分的にはそれでよかったかなと。
フランスでよかったなと思います。日本にいたら、また全然違っていたでしょうね。とにかくマウロと出逢って、自分のやる気次第で評価してもらえるということがわかった。自分はなんでポストを上げてもらえないんだろう? その気持ちがすごく溜まっていたときだったので、バーン! と爆発したような感じでしたね。マウロはやればやるだけ、評価してくれた。労働時間もすごく長かったんですけど、すごく濃い時代でしたね。3年分くらいを1年でやっていたような。いい意味で最後まで諦めない。やらなければいけない。諦める道はない。「はい」か「いいえ」。やるか、やらないか。真ん中はありせん。それをミラズールでは教わったと思います。最後の最後まで諦めないで、いいものを出す。チャレンジする。
M やっぱり、すごい出逢いですね、マウロさんとは。
C 人生変わった、と言っていいと思います。ご縁もあります。フランスに行って、出逢ったのがなんでアルゼンチン人だったのかなということもあります。きっと、彼も彼でアルゼンチン人だから評価してもらえなかった、ということがあるんでしょうね。
M きっとあったでしょうね。マウロさんは(アラン・)パッサールシェフに師事されて、たくさんのフランス人の方々と一緒に仕事をしていたでしょうから。きっといろいろな苦労をされていたのかなと思います。

le monologue de Marie quatre
progres
進行形
2011年にミラズールに伺ったときから、ずっと千帆さんの存在に刺激を受けつづけていますが、今回いよいよ彼女と「つながった」と思いました。心が通いあった。そう感じました。対談させていただいたことは大きいのですが、ディネのwelcomingの際の印象はもちろん、予約させていただいたときから「待っていますね」という温かさを受けとることができました。もはや彼女は星付きレストランのシェフのひとりとして、誰もが認めるキャリアを積まれているわけですが、2018年に行くことができて、ほんとうによかったと思います。
日々、動き、進んでいる方なので、正直なところ、もう明日どうなるかはわからない。いまはあの場所で料理を作っている彼女ですが、おそらく終の住処というわけではないでしょう。あの日、あの場所で、ディネを、デジュネをいただき、ともに語りあうことができた。それは私にとって大きなことでした。
パリの食事情も、これからどんどん変わっていくと思います。また、彼女はパリのテロも間近で経験されています。以前のVirtusは、テロが起きた場所のすぐ近くでしたから。それはとても切実なことだったと思います。それだけに、最新の彼女にあのとき逢えたということは、とても貴重なことです。いまの私が、いまの千帆さんに逢えた。来年の私はまた違う私ですから。
2018年11月。お逢いして対談するのは、まさに「このとき」だったのだと思います。さまざまなご縁で実現したことをうれしく思います。
Text:Toji Aida
Photo: Marie Akiyama/Toji Aida

![[ワイナート]The Magazine for Wine Lovers](https://winart.jp/winart_kanri/file/img/common/img_header_winart.png)